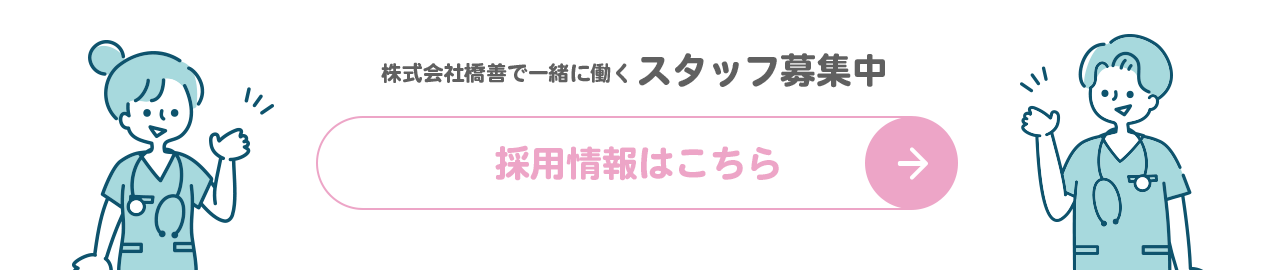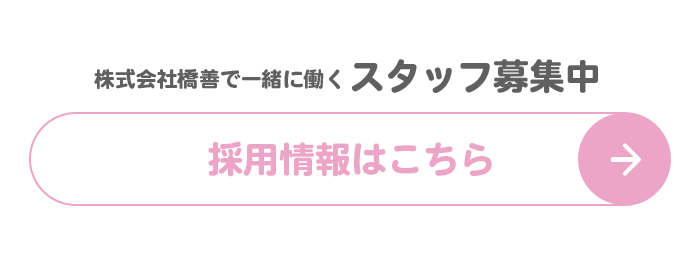訪問看護ステーションが提供しているサービスについて解説
「家族の介護で毎日不安を感じている…」「訪問看護でどんなサービスを受けられるの?」「利用手続きや料金がよく分からない…」そう思う方もいるかもしれません。
実は、訪問看護ステーションでは健康状態の管理から医療処置、リハビリテーション、終末期ケアまで幅広いサービスを提供しており、ケアマネジャーと連携して最適なケアプランを作成することで、在宅での安心した療養生活を実現できるのです。
この記事では、訪問看護の5つの主なサービス内容から利用開始までの流れ、料金体系まで分かりやすく紹介します。
訪問看護ステーションとは?基本的な仕組みを解説

訪問看護ステーションとは、看護師などの専門スタッフがご自宅に伺い、医師の指示に従って医療ケアや日常生活のサポートを行うサービスのことです。病院ではなく、いつもの家で安心して治療や介護が受けられるため、ご本人だけでなくご家族にとっても心強い支えとなります。
ここでは、訪問介護ステーションの仕組みを深堀していきます。
訪問看護ステーションの役割と目的
訪問看護ステーションの一番大切な役割は、病気や障がいのある方が自宅で安心して暮らし続けられるように、医療と生活のサポートをまとめて提供することです。看護師やリハビリの専門家が定期的にお宅を訪問し、体の状態を確認したり、必要な処置やリハビリを行ったり、ご家族へのアドバイスもします。
また、病院や介護サービスともしっかり連携し、利用者様を中心にしたサポート体制を整えることも大切な役割です。主治医とも密に連絡を取り合い、病状に変化があったときには、早めに病院の受診や入院の手配ができるようにしています。
在宅医療との違いとメリット
訪問看護と在宅医療はどちらも自宅で受けられる医療サービスですが、内容や利用の頻度が少し異なります。在宅医療では、医師が月に1〜2回ほど家に来て診察し、治療の方針を決めますが、訪問看護は週1回から毎日まで、利用者様の体調や必要に応じて頻繁に訪問し、継続してケアを行います。
訪問看護の大きな特徴は、住み慣れた自宅で安心して療養できることです。入院によるストレスを避けながら、専門的な医療を受けられます。また、家族への介護のアドバイスや気持ちのサポートもあるので、介護の負担が軽くなり、家族みんながよりよい生活を送れるようになるでしょう。
訪問看護師の資格と専門性
訪問看護を行う看護師は、国家資格を持つだけでなく、自宅での医療に必要な専門知識やスキルを身につけたプロの医療スタッフです。病院での経験を活かしながら、ご自宅という環境に合わせたケアの方法や、ご本人・ご家族との丁寧なコミュニケーションの力も持っています。
中には、がんや緩和ケア、心のケア、皮膚や排泄ケアなどの分野で、さらに深い専門知識を持つ「認定看護師」や「専門看護師」もいます。また、医療機器の使い方や急な体調変化への対応にも慣れており、ご自宅でも安心して医療を受けられるようサポートする体制が整っています。
訪問看護ステーションが提供する5つの主なサービス
訪問看護ステーションでは、利用者様の体の状態や生活の様子に合わせて、体調のチェック、医療的な処置、人生の最期を支えるケアまで、さまざまなサービスを行っています。これらはすべて医師の指示に従って行われ、ご本人が自宅で安心して過ごせるように、一人ひとりに合った内容を組み合わせて提供されます。
ここでは訪問看護ステーションが提供する5つのサービスについて解説します。
健康状態の管理サービス
健康状態の管理サービスでは、血圧や体温、脈拍、呼吸などを定期的にチェックして、日々の体調を見守ります。看護師がこまめに体調の変化を確認することで、病気が悪化する前に気づくため、早めの対応が可能です。必要に応じて、体重や血糖値の測定なども行い、糖尿病などの慢性的な病気の管理をサポートします。
また、病気や障害による不安や抑うつ状態に対して、専門的なカウンセリングや心理的サポートを提供し、利用者様との信頼関係を築きながら精神的な安定を図ります。こうした体や心の状態についての情報は主治医に共有され、治療の方針を決める参考にもなります。
治療促進のための看護サービス
医師の指示に従って、専門的な医療処置を自宅で安全に行います。たとえば、人工呼吸器や酸素を使う機器などを使う場合には、機械の使い方や注意点を丁寧に説明し、きちんと動いているかの確認も行います。必要に応じて、24時間体制での管理も可能です。
また、薬の飲み方や保管方法、副作用に関する注意点もわかりやすく説明し、薬の飲み忘れや重複を防ぐための「お薬カレンダー」の使い方もご案内します。点滴や注射、傷の手当て、カテーテルの管理などの高度な医療処置も行っており、血液や尿の検査も自宅で受けることができます。
終末期の看護サービス
利用者様が人生の最期まで自分らしく過ごせるように、体の痛みや心の不安、家族との関係など、さまざまなつらさの軽減をサポートするサービスです。痛みをやわらげるためには、医師と連携して薬を調整したり、息苦しさや吐き気といった症状にも専門的に対応します。
自宅で最期を迎えたいという希望がある場合には、事前の準備や手続き、万が一の時の対応についてもわかりやすく説明し、24時間いつでも連絡がとれる体制を整え、ご家族が安心して見守れるようお手伝いします。
相談・コンサルティングサービス
訪問看護では、療養中の生活に関するさまざまな相談に対応しています。たとえば、自宅で安全に過ごせるようにするための住宅改修では、手すりの取り付けや段差の解消、トイレやお風呂の使いやすさなどについて、利用者様の体の状態に合わせたアドバイスの提供も可能です。
また、車椅子や介護用ベッド、歩行器などの福祉用具を使用したいときには、状態に合った道具の選び方をサポートし、専門の相談員と協力してお試し期間を設けることもできます。
さらに、介護をするご家族の負担を少しでも減らすために、介護のコツをお伝えしたり、一時的に介護を代わってもらえる「レスパイトサービス」の活用方法なども含めて、トータルで支援しています。
リハビリテーションサービス
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といった専門スタッフが、利用者様の体や頭の働きを保ち、少しでも良くなるようにサポートします。
関節が動きにくくならないようにする運動では、ストレッチや筋トレなどを利用者様の体の状態に合わせて行い、無理なく続けられる運動プログラムを作ってサポートします。
また、歩く・立ち上がる・トイレやお風呂に入るといった日常生活の動作を練習し、できる力を活かして、なるべく自分でできる生活を目指します。
訪問看護サービスの利用条件と対象者

訪問看護サービスは、医療保険と介護保険の2つの制度により利用することができ、それぞれ異なる利用条件と対象者が設定されています。
ここでは、訪問看護サービスの利用条件と対象者について詳しく解説します。
医療保険で利用できる条件
医療保険による訪問看護は、年齢に関係なく病状や医療処置の必要性に応じて利用できます。主な対象となるのは、人工呼吸器や気管カニューレ、胃ろうなどの医療機器を使用している方、がんの末期や難病指定を受けている方、精神科疾患で通院が困難な方などです。
医療保険を使う場合、週に3回までの訪問が基本ですが、特別な事情があれば毎日の訪問や、24時間体制での対応も可能です。ただし、利用するには医師が「訪問看護指示書」という書類を出す必要があり、それに沿ってケア内容が決まります。
介護保険で利用できる条件
介護保険による訪問看護は、40歳以上で要介護認定または要支援認定を受けた方が対象となります。65歳以上の方は原因疾患を問わず利用できますが、40歳から64歳までの方は特定疾病(がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など16疾病)が原因で要介護状態になった場合に限り利用可能です。
介護保険では利用者様の要介護度に応じて月の利用限度額が設定されており、その範囲内でケアマネジャーが作成するケアプランに基づいてサービスを利用します。
たとえ医療的な処置が必要な場合でも、体調のチェックや薬の管理、リハビリなど、生活を支えるケアが中心であれば、介護保険の対象になります。
年齢制限と病状による制限
訪問看護サービスには基本的な年齢制限はありませんが、適用される保険制度により利用条件が異なります。小児から高齢者まで幅広い年齢層が対象となり、特に小児の場合は医療保険が適用されることが多く、発達のサポートや家族へのアドバイスも含めた総合的なケアが行われます。
サービスを受けるには、まず医師が「訪問看護が必要」と判断することが前提です。感染症の方には感染を広げないように特別な注意をして対応し、精神的な病気がある方には専門知識を持った看護師が対応します。
直接応募の場合のみ
就職お祝い金制度あり(正社員:10万円、パート:5万円)
お問い合わせ
さまざまなお悩み解決のために、
全力でサポートいたします。
お困りごとやご不明な点などありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
お電話での
お問い合わせ
 072-247-8311
072-247-8311

 Webサイトからお問合せ
Webサイトからお問合せ