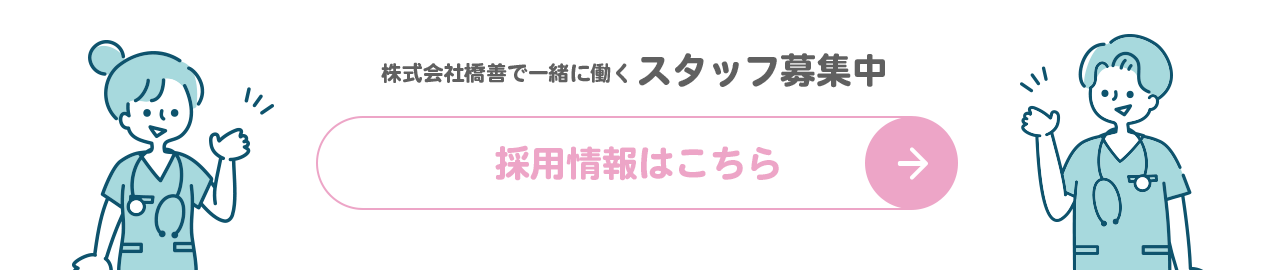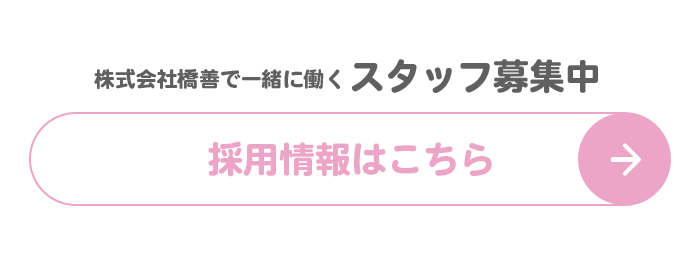訪問看護業界の求人について市場の動向などを調査(2025年版)
「子育ても落ち着いてきたので、そろそろ仕事に復帰したい。」「訪問看護なら働きやすいと聞いたけど、本当に安定して働けるの?」「未経験でも大丈夫?求人の動向や今後の需要が知りたい。」そう思う方もいるかもしれません。
訪問看護業界は今、求人数が増加し、未経験者へのサポート体制も充実しています。高齢化の進行と在宅医療の推進を背景に、2025年現在では安定的な需要が続いており、働き方を見直したい看護師にとって有望な選択肢と言えます。
2025年の最新データをもとに、訪問看護業界の求人動向や求められる人材像、給与・待遇の実態、地域差などについて詳しく解説します。
2025年の訪問看護業界の求人市場の全体像

2025年の訪問看護業界は、求人の量と質の両面において注目が高まっています。高齢化の加速と在宅医療のニーズ拡大により、訪問看護の需要は急増しており、それに比例して求人市場も活発化しています。
ここでは、訪問看護業界の求人市場の地域差や業界の全体的な流れを把握していきます。
求人数の推移と前年との比較
2024年から2025年にかけて、訪問看護に関する求人は都市部を中心に大幅に増加しています。特に訪問看護ステーションの新設が相次ぎ、常勤・非常勤を問わず多様な雇用形態での募集が多く見られます。これは病院のベッド数抑制政策や在宅医療への移行が進む背景によるものです。
また、「訪問看護未経験者歓迎」や「教育体制充実」といった求人が増えており、求職者にとっては門戸が広がっていると言えるでしょう。
訪問看護ステーションの増加とその影響
全国の訪問看護ステーション数は、2025年現在で18,743件となり、10年前の6,590件と比べて約2.8倍に増えています。これほど急激に増えた背景には、「入院よりも自宅での療養を進めよう」という国の方針や、病院のベッド数を減らして在宅医療を支える体制を強化する動きがあります。
特に都市部では、介護施設などと連携しやすいことや、収益が見込めることから、新しく参入する事業者が増えています。また、すでに訪問看護を行っている事業者が複数の拠点を持つ動きも進んでおり、市場全体の広がりをさらに加速させています。
参照元:令和7年度 訪問看護ステーション数 調査結果(一般社団法人全国訪問看護事業協会)
地域ごとに異なる求人状況
訪問看護の求人状況は、住んでいる地域によって大きく違いがあります。東京や大阪などの大きな都市では、訪問看護ステーションが多くあり、求人数も多いため、自分に合った職場を選びやすい環境です。
一方で、地方では事業所の数が少ないうえに、もっと深刻な人手不足に悩まされています。そのため、地方の訪問看護ステーションでは人材を確保するために、都市部にはない特別な待遇を用意するケースが増えています。
地域に根ざした働き方ができるため、じっくりとキャリアを築いていきたい看護師にとっては、地方での勤務も魅力的な選択肢になっています。
求人が増加している背景と業界トレンド
訪問看護の求人が年々増加している背景には、日本社会の構造的な変化と医療政策の大きな転換があります。特に高齢化の進行、医療の地域分散化、そして政府による在宅医療の推進は、訪問看護という働き方とサービス形態を大きく後押ししています。
ここでは、業界の根本的な変化と求人増加の要因を詳しく解説します。
高齢化社会と在宅医療のニーズ拡大
2025年には、いわゆる「団塊の世代」がすべて後期高齢者(75歳以上)となります。この急激な高齢者人口の増加は、医療・介護サービスの需要を高めています。
高齢者の多くは、病院ではなく住み慣れた自宅で医療ケアを受けたいと希望しており、それに応える形で訪問看護の役割が重要視されているのです。この結果、訪問看護の人材確保が課題となり、各地で求人活動が活発化しています。
病院から在宅への医療シフト
医療費の高騰を背景に、国は入院医療から在宅医療への転換を強く推奨してます。特に慢性疾患やターミナルケアに関しては、在宅での対応が経済的・心理的にも優れているとされ、医療機関側も積極的に訪問看護ステーションとの連携を進めています。
これにより、病院で働いていた看護師が訪問看護にキャリアチェンジする動きも見られ、求人市場は経験者・未経験者を問わず広く門戸を開いている状況です。
政府の在宅医療推進政策と補助制度の影響
国や自治体は、在宅医療の充実を図るためにさまざまな支援策を実施しています。たとえば、訪問看護ステーションの開設を支援する補助金制度や、地域包括ケアの整備予算、ICTを活用した訪問支援の導入助成などがそれにあたります。
こうした政策の追い風を受けて、新規のステーション開設も進み、求人の新規発生件数も年々増加傾向です。結果として、訪問看護は制度的にも安定したフィールドとみなされ、求職者からの関心も高まっています。
訪問看護師に求められるスキルと人物像

訪問看護は、病院勤務とは働き方が異なります。患者の生活環境に入り込んでケアを行うため、専門的な看護技術だけでなく、柔軟な対応力が重視されます。
ここでは、未経験者・経験者を問わず、訪問看護師に求められる資質やスキルについて解説します。
未経験者に求められる基本的な適性とは
訪問看護未経験の方に対しては、まず「人としっかり向き合う姿勢」がポイントです。病院と違い、訪問先では一対一の関係性の中で看護を行うため、コミュニケーション能力が非常に大切になります。また、医師や他職種との連携が必要なケースも多く、報告・連絡・相談が適切にできることも求められます。
基本的なバイタル測定や清拭、点滴管理といった看護スキルが身についていれば、訪問看護ステーション側で丁寧な研修や同行指導が用意されている場合も多く、未経験者の応募も十分に受け入れられる状況です。
経験者に求められる専門性と判断力
病棟経験がある看護師にとっては、訪問看護への転職は比較的スムーズな道と言えますが、それでも新たに必要とされる能力があります。それが「判断力」と「個別対応力」です。
訪問先では一人で対応する場面が多く、急変時の初期対応やリスク管理は自分の判断に委ねられます。そのため、これまでの臨床経験をもとに、的確に状況を捉える観察眼と対応力が重視されます。
さらに、在宅療養中の患者は疾患だけでなく生活全体に課題を抱えていることが多く、医療以外の視点からも関われる柔軟性が求められます。
「ひとりで訪問する」ことへの心構えと対応力
訪問看護の最大の特徴は、「基本的に一人で現場に入る」ことです。これまでチームで動いていた看護師にとっては、大きな変化となりますが、実はこのスタイルに魅力を感じて転職を希望する人も多くいます。
ただし、ひとりでの訪問には自己管理能力や緊急時対応の備えが不可欠です。そのため、ステーションによっては緊急時のマニュアル整備や、タブレットを活用した情報共有体制が整っており、安心して勤務できる環境づくりが進められています。
事前に見学や面談で業務の流れを確認し、自分のスタイルに合うかを見極めることが、長く働くうえでのポイントになるでしょう。
訪問看護の求人における給与・待遇の実態
訪問看護師として働くうえで、給与や待遇がどのようになっているかは非常に重要なポイントです。病棟勤務と比べて給与が高いというイメージを持つ方も多いですが、実際のところはどうなのでしょうか。
ここでは、訪問看護師の収入構造や待遇面、他職種との違いについて詳しく見ていきます。
訪問看護師の平均年収と報酬体系
2025年現在、訪問看護師の常勤の平均年収は約450万〜550万円程度が目安となっています。非常勤やパート勤務の場合は時給換算で2,000円〜2,500円台が主流です。
多くの事業所で、基本給に加えて訪問件数に応じたインセンティブが設定されており、経験やスキル、訪問回数によって給与に差が生まれています。管理者や主任などの役職につくと、年収600万円以上になる場合もあります。
地域や勤務先の規模、報酬体系によって金額に幅があるため、具体的な給与条件は求人情報や面談時に必ず確認しましょう。
病棟勤務との給与・働き方の違い
訪問看護と病棟勤務の最大の違いは、「夜勤がない」または「少ない」ことです。病棟勤務では夜勤手当込みで高い年収になるケースもありますが、訪問看護では日勤中心でも安定した収入が得られる点が魅力です。
一方で、勤務形態は比較的フレキシブルな反面、訪問スケジュールがタイトになることもあり、時間管理や自己調整力が必要です。急なキャンセルや訪問内容の変更が発生することもあるため、そうした変化に柔軟に対応できる方が向いているといえます。
オンコール手当やインセンティブ制度の有無
訪問看護師の給与面で注目すべきなのが、「オンコール手当」の有無です。オンコールとは、緊急時に備えて電話対応や夜間出動を行う体制のことを指し、これに対応する場合は別途手当が支給されるのが一般的です。
手当の金額は、1回あたり2,000円〜5,000円程度、出動すればさらに別途支給されるケースもあります。オンコールを担当するかどうかは選択制にしている事業所も増えており、子育て中の方や家庭の事情を考慮した働き方が可能なところもあります。
また、件数連動型のインセンティブ制度を導入しているステーションでは、一定件数を超えた分に報酬が加算される仕組みになっており、やる気やスキルによって収入を伸ばすこともできます。
直接応募の場合のみ
就職お祝い金制度あり(正社員:10万円、パート:5万円)
お問い合わせ
さまざまなお悩み解決のために、
全力でサポートいたします。
お困りごとやご不明な点などありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
お電話での
お問い合わせ
 072-247-8311
072-247-8311

 Webサイトからお問合せ
Webサイトからお問合せ